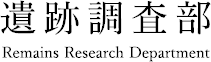荒屋敷遺跡
- 調査期間
- 5月~12月(予定)
- 場所
- 伊達市伏黒字六角
- 該当時代
- 弥生・古墳・古代・中世
- 調査原因
- 一般国道115号相馬福島道路の建設
荒屋敷遺跡は、昔の阿武隈川に沿って形成された自然堤防上に立地しています。昨年度実施した確認調査では、弥生土器や古墳時代~平安時代の土師器・須恵器が出土しています。遺構は、土坑・溝跡・小穴等が見つかっています。
5月30日のようす

荒屋敷遺跡の調査を開始しました。まずは、重機による表土剥ぎを実施しています。
6月18日のようす

表土剥ぎが終了した箇所について、遺構があるかどうか探しているところです。丸い小さい穴や、長軸が2~3mの長方形の輪郭が見え始めました。今後、掘り込みを行い、本格的に調査していく予定です。
6月26日のようす

土坑から古墳時代後期の土師器甕が出土しました。出土状況の記録を作成し、取り上げました。この後、室内で水洗いをし、接合します。当時のままの近い形に復元できそうです。
7月11日のようす

遺構が集中する調査区南端部の全景を撮影しました。土坑や溝跡の他、多数の小穴が見つかりました。小穴は、中世頃の建物跡の柱穴と推測されます。
9月13日のようす


土坑から多量の石とともに中世陶器の甕の破片が出土しました。この土坑が人為的に埋められた時に、陶器片も一緒に捨てられたようです。
9月18日のようす

中世陶器片が出土した土坑の全景写真です。
10月17日のようす

遺構の検出作業をしている様子です。土を削っていくと、地面の土とは違う色の輪郭が見えてきます。この部分が遺構と考えています。この写真を撮影した箇所では、3~4m程度の方形や直径20㎝前後の丸い遺構があることがわかりました。今後、こられの調査を実施していきます。
11月9日のようす


荒屋敷遺跡からは、土坑や小穴から古銭が約30枚出土しています。写真の古銭は、「祥符元寶(しょうふげんぽう)」や「政和通寶(せいわつうほう)」と判読でき、いずれも中国の王朝である北宋(960~1127年)の時代につくられたものです。これ以外の古銭についても、細片で判読できない資料もありますが、大半が北宋銭であることがわかりました。
11月21日のようす


調査も終盤に差し掛かったため、調査区の全景写真を撮影しました。上の写真は、「10月17日のようす」で紹介した調査区北部で、下の写真はこれより少し南の調査区中央部です。特に調査区中央部では多数の遺構が集中し、遺構を壊さないよう移動するのが大変でした。この後、調査は12月3日に終了しました。